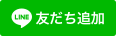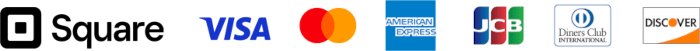某医師の方からの相談―自由診療や混合診療
混合診療に関するご相談でした。
日本では、混合診療は禁止されており最高裁の判例でも確定しています。
したがいまして、医師で「知りませんでした」という言い分は通りません。
混合診療は、健康保険部分は健康保険を利用し、自由診療と組み合わせるという意味で「混合」ということになります。
個人的に、社会道徳的に、ガンなどの高額治療の場合は、健康保険との併用を認めた方が患者のためになりますし、混合診療を行っている医師に道徳上倫理上の問題があるとは思いませんが、厚生労働省としては、①安全性、有効性が確認されていない医療が保険診療と「併せて」実施されてしまう、②保険診療により、一定の自己負担額について必要な医療が提供されているところ、患者に対して、保険外のエクストラマネーを要求できることが一般化してしまう―という点が制度趣旨です。
しかしながら、上記①については、時間的・場所的密着性が認められないのであれば「併せて」という定義に該当しないのか私見は疑問に思います。
次に、上記②については、保険診療で医師の「値決め」が決まっているのに、国が決めた「値決め」以上のエクストラマネーの要求が一般化するというのですが、そもそも、アメリカでは、メディケアはあるとはいえ、一般的に病院代は保険がありませんから、全額自己負担であり、どの範囲で治療を希望するかも患者の自由です。そもそも、上記②は、厚生労働省が保険診療として認めていない治療を患者が希望するから、医師法に違反しない範囲で、必要かつ相当な医学的根拠のある医業を提供しているものであって、保険外のエクストラマネーを要求するのがおかしいというのは不自然・不合理と言わざるを得ません。
日本では、多くの患者が行政訴訟を起こしていますが、それは、患者側が「混合診療を受ける地位」の確認を求めており、保険外の医療行為を求めているのですから、その点に対価が生じるのは当たり前のことではないかと思います。
しかしながら、日本では、健康保険を使用してしまうと、健康保険の「範囲を超えた診療が同時に行われる場合」、原則として、診療の全てが自由診療となるルールとなってしまい、自己負担となってしまうのです。
ですから、ここは健康保険、ここは自由診療という場合分けがしにくいというところがあります。
しかし、厚生労働省の発想は、時代遅れでしょう。患者が受けたい医療を受ければ良いのだと私見は思います。
こういう声もあるため、「特定療養費」に該当する場合は、保険診療内の医療行為には保険が適用されるという特定療養費制度がもうけられました。
そして、原則として、「混合診療禁止」は変わらないですが、保険との併用との関係から平成18年から保険外併用療養制度が始まっています。これは、ほんのわずかではありますが、保険の範囲を超えた部分を「評価療養」と、患者が希望する保険適用外の療養について併用を認める「選定療養」に関して、保険制度の併用が認められるようになりました。一例を挙げると、差額ベッド代など金額は僅少なものであると推認されます。
平成28年4月1日からは、患者申出療養というものも併用可能な保険外診療として認められており、ドクターの中には、「混合診療禁止との区別がつかない」という方も出てきています。
つまり、保険適用内診療以外に行われた療養について、①評価療養、②患者申出療養、③選定療養のみである場合には、上記①から③を自己負担として、その他を保険でまかなうことが可能になっています。
しかし、厚生労働省の「こだわりどころ」は、①科学的根拠のない医療の実施の助長(つまり、厚生労働省が認めない医療行為は保険診療の対象にしないこと)、②安全性や有効性は個別的に確認される(つまり、一部評価療養などでも安全性や有効性がなければ、否定される場合もあり全部が自由診療になる場合もある)、③一番多いのは、未承認の薬の使用であると思われる。その他の例外は人道的な見地からのものであり一般の開業医は参考にならないと思われる。
歯科医師の場合は、差額ベッド代、金属床の入れ歯代あど例外として認めてきた混合診療の一部拡大をするという報道もある。
厚生労働省は、「複数の医療行為であっても、不可分一体として保険適用するか判断する」というリスク要因がある一方で、保険外併用療養費制度がもうけられたという経緯である。
歯科医の場合は、
金属床総歯及び前歯の金属材料の差額のみという指摘もあるのであって、混合診療においては、グレーなところも残らないわけではないように思われる。
例えば、①サリバテストは保険が効かないから、歯周治療(保険治療)に訪れる患者に、サリバテストの自由診療代は請求せず、保険の再診料は請求しないという形で処理している歯科医師もいる。あた、②いったん保険治療の患者を診療室から出てもらい、再度入室してもらい自由診療を行うといったこともあり得るが、これらは、グレーである。
一例を挙げると、歯科医師の関係で、「安全性が確保されていなから保険の対象外」といわれても、あまり患者の理解は得られないように思われる。それでも、医師らは、定期指導や個別指導などでしばりをかけられており、現実と法律の狭間が衝突している部分といえる。
保険診療の治療の一部で自由診療の素材(インプラントやセラミック)を使用して、保険診療をしてしまうと、全体が自由診療になる恐れがありますので、よくご注意ください。
常態化していると個別指導や監査に発展することがありますので、お早目に相談ください。
参考、最高裁平成23年10月25日判決
同判決では、制度があるものを除き、混合診療として、法86条の解釈問題として、その先端医療が評価診療の要件には自由診療のみならず保険診療についても保険給付はできないと結論付けている。
この判例は、「混合診療禁止の原則」について第一審が違法との判断を示し(東京地判平成19年11月7日判タ1261号121頁)、衝撃を与えた裁判例である。しかし、二審で覆されたものの、多くの裁判官の個別意見(田原睦夫補足意見、岡部喜代子補足意見、大谷剛彦補足意見、寺田逸郎意見)は、この問題の根深さを示すものと考えられる。