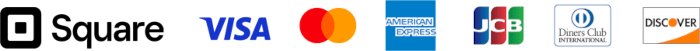看護師のレントゲン撮影と刑事責任――形式論に抗して、理論弁護のプラクティス ~医療機関が狙われる行政法規違反と高山佳奈子教授の「罪を犯す意思」を巡って~
看護師のレントゲン撮影と刑事責任――形式論に抗して、理論弁護のプラクティス
~医療機関が狙われる行政法規違反と高山佳奈子教授の「罪を犯す意思」を巡って~ 1 コラムの前提知識
診療放射線技師法は、X線撮影の業務は原則として、医師・歯科医師・診療放射線技師に限定しており、看護師はこれに含まれていません。そして、医師法は、無資格医業禁止の規定がありますが、無断X線撮影は特別法として診療放射線技師法が優先する関係にあります。
刑法では、構成要件的事実の認識を欠く場合は故意が否定され不可罰となります。しかし、違法性の錯誤の場合は、法の不知は害するとされ故意は阻却されず処罰されます。もっとも、違法性の意識の可能性が責任故意(責任の要件としての違法性の意識の可能性)の要素になっている刑法学者もおり、違法性の意識の可能性がない場合は、不可罰となるものの、同じ「故意」であるため、構成要件的故意と責任故意は峻別されていない理論的状況にあります。 2 医療の現場が「犯罪化」する瞬間
医師がいそがしく患者さんをお待たせしています。そんな中、医師から「山田さん、レントゲンボタン押しておいて」という声が聞こえてボタンを押してしまった場合、どうなるのでしょうか。
医師法ないし診療放射線技師法違反(無資格医業)の客観的構成要件に該当しかねないことが多いでしょう。すなわち、診療放射線技師法は、X線撮影等を医師・歯科医師または診療放射線技師に限定する構造を採用しています。それゆえ、看護師であっても、単独でX線装置を作動させる行為は、医師の一般的指示があっても、原則としてここに抵触し得ます。
しかし、主観的構成要件に該当するかは、階層的分析が可能なのです。故意というのは、「ボタンを押すことを認識していた」というだけであるという説明する弁護人がいたら交代させましょう。
3 故意とは
故意というのは犯罪事実の認識をいいます。これに対して、違法性の意識は禁止されていることの認識をいいます。多くの学説は、違法性の意識の可能性は故意の内容を構成すると考えているといえます。
看護師の犯罪的な傾向が看護師の「心理」に内面化されていたかという視点というアプローチから故意は弁護人は故意を「再点検」します。
高山佳奈子教授は、故意は、意思ではなく、「犯罪事実の認識」をいい、責任要素とされます。そして、看護師の認識内容も、詳細かつ階層的に、「無資格医業」という客観的構成要件事実を認識していたか、さらに深めると、「レントゲン撮影が医療行為に該当すると認識していたか」「医師法ないし診療放射線技師法から見て山田看護師がした行為が無権限性があり、医師のコントロールから逸脱したかなど医師法ないし診療放射線技師法が着目する属性する認識」はどうであったかを突き詰めるのです。
4 刑事弁護の第一線~意味の認識の欠如(故意の否定)
山田看護師は、「医師の指示があること」で自己の行為が正当な診療放射線技師法が予定する資格者による作業・監督の枠組みないしコントロール下にあると医師法ないし診療放射線技師法が着目する属性についての認識を誤信していたといえるのです。
弁護人としては、「医師の指示があること」によって、自己の行為が正当な一連の医療プロセスの管理下にあると誤信したといえるかもしれません。
そうすると、一般的な街弁(医師にありがちな顧問弁護士)が、「故意とは、レントゲンボタンを押すことです」というのは誤りなのです。
すなわち、この誤信は、無資格医業という犯罪の実質をなす属性ないし意味づけの認識を欠いた結果であるとするならば、故意犯は成立しないと解するのが正当なのです。
高山教授の見解は、「刑法が着目する属性」の認識が欠ける以上、故意を認めるべきではないと指摘しているのです。
5 違法性の錯誤ではないこと
このアプローチは、山田看護師の誤信を「違法性の錯誤」ではなく、構成要件的事実の認識の中に「意味の認識」を取り込むことにより、「事実の錯誤」と考えるのです。そして、事実の錯誤である以上、責任非難が妥当しないと考えるのです。
6 責任阻却としての違法性の意識の可能性~規範的要素を巡って
仮に、故意は認められてしまったとしても、不起訴へと動くため、その行為について、法的な非難を向けることが正当であるかという視点から、「違法性の意識の可能性」という概念を検討することになります。
刑法は、構成要件に該当し、違法かつ有責な行為と解するものであるところ、高山教授は、違法性の意識の可能性を責任阻却事由と位置付けるのです。
刑罰は、自由保障と国民からの責任非難からの構造を採る以上、責任の阻却事由として、「違法性の意識の可能性」を位置付けます。
7 違法性の意識の可能性など認められるのか~知っている弁護人とそうでない弁護人との違い~
まず、全てが、正式裁判になるわけではありません。検察官では、不起訴や略式罰金命令で終結する事例もあります。
したがって、看護師の誤信(医師の指示で違法性が阻却されるか)は、通常は、「違法性の錯誤」の問題として扱われています。
ゆえに、看護師が刑法上の禁止を認識し、法に従ってレントゲンボタンを押さないというオプションがあったかどうかが問題となるのです。
この点、違法性の意識の内容については、抽象的に社会侵害的というものでは足りず、具体的なレントゲンボタンを押すという行為と関連付けられた刑法上の禁止との関連との関係でレントゲンボタンを押さないというオプションがあるのかを検討することになるのです。
8 弁護人の視点~看護師の常識やインテリジェンスは~
違法性の意識の可能性を判断する基準は、行為時点の看護師の知的水準を前提として、合理的に違法評価に到達し得る道が与えられているのかといった規範的な評価なのです。
そもそも、想像がつきにくいですが、国家刑罰権の出動は、処罰する側とされる側が対等でなければなりません。一例を挙げると、医師の指示の合理性はさておき、高山教授の立論は、検察が、「法に従った動機付け」のための手段を奪っているならば、責任非難ができなくなり責任阻却を認めるべきと主張します。これは、日本刑法学で伝統的に説かれる『期待可能性(規範に従うことが期待できたか)』の議論とも整合するものですが、高山教授は期待可能性論はあくまで反対動機の形成可能性のものとしており、彼女が二元論で語る一つである「違法性の意識の可能性=「法に従った動機づけが与えられていたかを問う責任阻却要件」(自由保障の視点)とは峻別されます。
この点、公的立場にある病院長の指示などがある場合には、その行為が、ほぼ行政機関に近しい上下関係者から、助長・促進されているのですから、刑法上の禁止との関連との関係でレントゲンボタンを押さないというオプションがなく、法を守るという動機付けのオプションがないのです。このように、高山教授は、検察の側が、「法に従った動機付け」のための手段を奪っているのであれば責任非難することはできず、広く責任阻却を認めるべきであると主張しています。
これは、看護師一般ではなく、山田さんという看護師のキャリアや立場、社会的地位、知識などにも左右されるものといえ、看護師が組織の責任者からの指示を信頼した場合は、処罰を行う側の不意打ちに当たるのであって、違法性の意識の可能性が否定され、責任がないから無罪ないし不起訴にすべきという立論を展開することができるのです。
9 故意は、「レントゲンボタンを押すこと自体を分かっていること」だけではないこと
看護師が組織の責任者からの指示を信頼した事実は、処罰者の「不意打ち」に当たり、違法性の意識が否定され責任故意の問題になり得ることを意識される必要もあるのです。
10 この看護師さんのレントゲンボタンを押してしまった事例については、医師法ないし診療放射線技師法の機械的な法的判断があるでしょう。ただ、機械的な法のあてはめと、刑法に詳しい弁護士とのあてはめは異なります。
この事例では、「責任要素」を故意、すなわち侵害性の内面化による積極的根拠づけと、違法性の意識の可能性(自由保障)による消極的な阻却に峻別して、行政犯や行政命令に従ったに近しい構造を採用するとき、意味の認識の欠如(故意否定)又は、「動機付けの可能性の欠如」(責任阻却)を追求することになります。
11 高山理論を巡っては、刑法上の禁止の核心的意味を帯びていることを理解しているのかというのを評価していくアプローチなのです。医師法ないし診療放射線技師法でいえば、「無資格性」「逸脱性」という犯罪の属性の意味の認識を欠いていたことが高山佳奈子教授に基づく故意否定の主張なのです。また、高山理論が二段構えで主張する責任阻却は、看護師が医師法ないし診療放射線技師法に従うためだけの合理的条件を与えられていたのかという観点を問題にしています。すなわち、高山教授は、「規範的意味を含む事実の認識」を構成要件的故意と捉え、形式的な「レントゲンボタンを押した」といった物理的行為の認識では足らないと指摘しています。
そして、違法性の意識の可能性は責任の要件としており、これが欠けると、責任が阻却されるのです。例えば、保健所の検査でも黙認されたところ、検察官交代に伴い問題視されることになったということはあり得ることです。
高山教授は、特に行政庁や公的機関が誤ったメッセージを送っていた場合に、責任阻却を認める立論(=国家刑罰権からの市民の自由保障)をされます。
12 刑事弁護を諦めないため、理論的に雑な「ヤメ検」が良いとは限らない
高山教授は、罪刑法定主義や個別責任主義(行為と責任の同意存在の原則の徹底)を重視しながら、処罰の対象を厳密に限定する機能を果たしています。
警察官や検察官は、上記のケースでは、「レントゲンボタン」を押すことの社会的意味の追求まではしていないかもしれません。しかし、被告人は自分の行為の意味付けや色合いを理解していたのか、国家はそれを支える情報と制度を提供していたのか―この2つの軸(故意と違法性の意識を一つの軸で処理するのではなく峻別すること)を理論的に提供しているのです。
高山佳奈子と松宮孝明は、刑事弁護における最後の防衛ラインといえるでしょう。
高山教授は、「刑法は、人間を処罰する道具ではなく、処罰されてはならない人間を見極める道具」であるとします。このような立論に照らして、最後まで刑事弁護は諦める必要がないのです。
一例を挙げれば、レントゲン撮影の事例について、「病院長・事務長に尋ねたところ、医師の指導・監督の下に行っているので全く問題ないとの確答を得た」という事実関係の下では、「行為者の知識水準を重視して責任が阻却された点は正当なものと評価しうる」と考えられるのです。
弁護人は、力業や手続的デュープロセスのみならず、刑法理論を用いることで、「まじめに働いていた看護師さんが、不意打ちの刑罰が降らないようにするために」 刑法解釈論を展開することも仕事なのです。
13 例えるならばこんな意見書を目指します。
本件は、X線撮影業務における資格境界ないし業際の理解不足が背景にあり、構成要件的事実の認識(規範的属性の意味合いの認識)を欠く可能性が高い。被疑者は「ボタン押下=撮影実行」との法的意味(資格限定や院長の指示があれば適法であれば思っており現場の医師の指示があればこれを回避するオプションはなかった)を認識していない。ゆえに、事実の錯誤として故意は否定。仮に構成要件的故意肯定でも、明確な指揮命令・恒常的運用・人員体制等のもと、遵法行動の選択可能性は実質的に乏しい(違法性の意識の可能性に疑義)。是正完了、研修実施、再発防止策稼働。医療提供体制への配慮からも不起訴(起訴猶予)相当。
以上